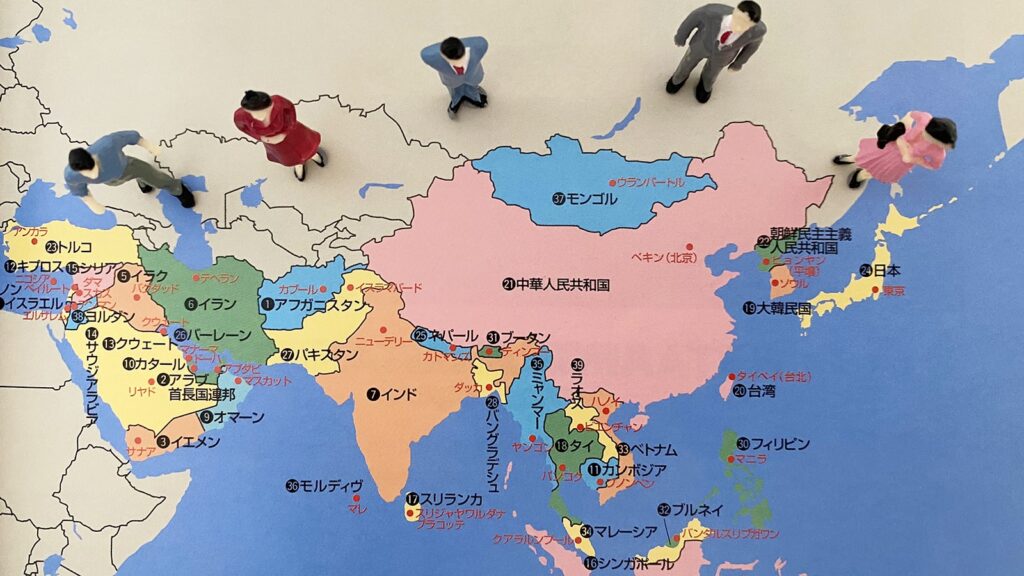
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
日本人の目から見たミャンマーという国が日本の文化に合っていることから、当社では外国人雇用の中でも特にミャンマー人をオススメしております。
しかし反対に、ミャンマー人から見た日本人はどのような印象なのでしょうか?
互いの印象や共通点、異なる点を理解すれば、より良い関係が築きやすくなるでしょう。
今回は、ミャンマー人が日本に来ようと思ったきっかけや、それぞれの国の共通点、実際に日本に来て困ったことなどをご紹介。
そこから、受け入れの際の注意点などを考えていきます。
今後、ミャンマー人の採用をご検討の企業様はぜひご覧ください。
日本に来よう、働こうと思う理由は?
昨今の円安の影響で、発展途上国から見ても出稼ぎ先としての魅力がなくなりつつある日本。
しかし、ミャンマーでは海外での働き先としての日本は根強い人気があります。
その理由のなかでも大きいのは、日本語に触れる機会、学習する機会の増加ではないでしょうか。
というのも、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し認定する試験である日本語能力試験の2023年7月の受験者数は9万人。
この人数は、日本、中国に次いで三番目に多く、非常に受験者数が多いことが分かります。
それも、5年前の2018年7月は約12,000人であったため、急激に人数が伸びているようですね。
(参考:日本語能力試験)
また、ミャンマーにあるヤンゴン外国語大学とマンダレー外国語大学においては、学部、修士、専門課程、夜間部の4コースが設置されているうえ、日本語教師育成コースも設置されています。
両校の日本語学科は人気が高く、入学するには高得点を取得する必要があります。
つまり、大学(日本語学科)卒のミャンマー人は、それだけでも比較的優秀であることが証明されるでしょう。
日系企業の進出や日本人訪問客の増加に伴い、日本語を使用する就業機会も劇的に増加していることから、それに伴い、学習希望者も増えているといえます。
また、歴史的な理由、宗教の理由、国民性等から、比較的親日家の多いミャンマー人にとっては、日本は馴染み深く、憧れの対象でもあるのです。
母国で日本語を学び、実際に日本に来て働き、技能面も日本語能力も向上を図りつつ、母国に帰ってそれらを活かす道もあります。
ミャンマーと日本との共通点は?
日本では無宗教の方も多いですが、基本的には仏教国と言っても良いでしょう。
そして、ミャンマーは熱心な仏教国です。
宗教的に見て共通点がある(理解がしやすい)ことは、互いにとって安心しやすいポイントです。
お寺にお参りに行ったりするのも同じです。
しかし、日本のお正月は1月ですが、ミャンマーは4月。
人によっては4月に里帰りをするため母国に帰りたい場合もあるので、注意が必要です。
また、身近なところで言うと、食べ物の主食はお米です。
ただし、調味料などは一部、日本では手に入らないものもありますが…
主食が共通していることは大きいのではないでしょうか。
イスラム圏その他のように、豚は食べてはいけないなどの制限も特にありません。
基本的には食べ物のことで困ったり、トラブルになったりすることは少ないでしょう。
日本に来てとまどったことは?
ミャンマーには挨拶をする習慣がないので、日本でも挨拶をしなかったことで、礼儀がなってないとみなされることがあります。
しかしそれは習慣としてないこと、知らないことなので仕方がありません。
無礼な人と決めつけるのではなく、日本では挨拶をする文化だ、ということを教えてあげる必要があります。
あとは、時間に厳しいことにも驚くそうです。
待ち合わせ時間に遅れると日本人はすごく謝りますが、ミャンマー人はそうでもありません。
ただし、日本人は他人に対しても時間に厳しく、人身事故で電車が止まった際に、自分の時間の心配ばかりして、親切ではなくなる人も少なくない印象とのこと。
互いにストレスとならないためにも、一緒に仕事をする上では、時間に対する感覚はある程度擦り合わせをしておく方が良いでしょう。
あとは、ミャンマーではあっても10年に一度くらいしかない地震。
日本は地震が多くて非常に驚いたそうです。
ミャンマー人に限らず、地震を経験したことがない外国人労働者は少なくありません。
受け入れた外国人労働者が地震の被害に遭わないよう、地震のことや、起きた際の身の守り方や避難経路などを教えておくことが必要でしょう。
受け入れ企業が気をつけるべきこと
ミャンマーは規則やルール、マナーなどがあまりありません。
反対に日本には規則やルールが多く、それも、多くの日本人は子どもの頃から身につけ、自然と守っているレベルです。
そうした意識の違いは、日常生活や仕事においても影響する場合があります。
前述の時間のこともそうですし、例えば交通ルールなども知らない場合があります。
本人の安全のためにも、周囲へ迷惑をかけないためにも、受け入れ企業が教育することも必要になってくるかもしれません。
また、整理整頓や清掃など衛生面に関しても、日本は幼い頃から教育されていますが、ミャンマーも含め、世界では日本ほど徹底した保健・衛生教育がされている国の方が少ないくらいです。
職場環境や健康の維持のためにも、こうした部分は日本の基準に合わせてもらうようにするべきかと思います。
本人がどこまで日本の文化や環境に適応しているかを見極め、しっかり指導・監督しましょう。
まとめ
ミャンマー人の方の目線で見た日本、いかがでしたでしょうか?
日本では当たり前のことも、海外ではそうではないことも多いですよね。
そうした違いを互いに知った上で、でも、日本で働く以上はある程度あわせてもらわないといけない部分もあれば、反対に認めてあげるべき部分もあるでしょう。
そこは受け入れ企業と本人とで話し合う機会を設け、行き違いや認識違いが起きないように注意が必要です。
ただ、そこをしっかりしていれば、基本的にはミャンマー人と日本人とは相性が良いので、良い仕事仲間になれるでしょう。
ミャンマー人の雇用に関して疑問や不安のある方は、まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、あなたの聞きたい質問やお悩みについてもアドバイスさせていただきます。
貴社の状況をヒアリングし、貴社に合った外国人採用戦略や支援計画、フォロー体制のご提案も可能です。
どうぞお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール









