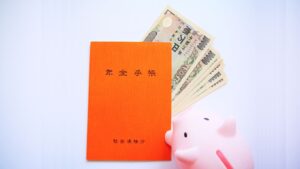外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
外国人労働者だけでなく、外国人観光客も激増している日本。
空港や観光地では免税店を多く見かけますが、ここで免税対象となるのは非居住者のみとなります。
日本に住み、働いている外国人労者は日本人同様、消費税も払わなければいけません。
では、消費税以外の税金についてはどうなのでしょうか?
今回は、外国人労働者が日本で納めなければいけない税金の種類と注意点、受け入れ企業が気をつけるべきことについて解説します。
今後、はじめて外国人労働者を受け入れようとされている企業のご担当者様は、ぜひご一読ください。
外国人労働者も納めなければいけない税金とは?
日本在住の外国人労働者が支払うべき税金は主に3つ。
消費税・住民税・所得税です。
順番に詳しく見ていきましょう。
消費税
冒頭でもあったとおり、日本に居住している(6ヶ月以上滞在している)場合は、外国人であっても、日本の消費税を支払う義務が発生します。
こちらは働いている、働いていない、給与の高い低いなどの経済状況に関わらず、物やサービスを購入する際には、平等に支払いの義務が発生します。
こちらは日々の生活の中で、購入時に支払う税金なので、滞納する心配はありません。
住民税
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっていれば、外国人でも支払い義務が発生します。
(1月2日以降に日本から出国した場合でも同様)
住んでいる自治体に支払う地方税で、道府県民税と市町村民税の2種類で構成されています。
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税の支払いには2つの方法があります。
1つは給与から天引きする「特別徴収」。
会社があらかじめ給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。
会社で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。
もう1つは自分で支払う「普通徴収」。
毎年6月頃に、市区町村から住民税の支払い案内(納付書)が手紙で届きます。
この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って、金融機関やコンビニなどで支払います。
所得税
所得税とは、所得に対して発生する税金で、1月1日から12月31日までに得た所得額に応じて納税額が決まります。
「所得」とは収入から必要経費を引いたお金のこと。
会社勤めの場合は、給与や賞与などの収入から給与所得控除を差し引いた金額を指します。
企業に雇用されている場合は、所得税は給与から天引きされているので、基本的には外国人労働者自身で納税をする必要はありません。
ただし、自営業や副業で個人事業主として収入を得ている場合は確定申告が必要。
給与収入以外の所得分も忘れずに納税するようにしましょう。
滞納するとどうなる?
前述のとおり、住民税も所得税も給与からの天引きのみの場合は、基本的に滞納をする心配はありません。
しかし、何らかの事情で住民税を普通徴収にしている場合や、副業などで別の収入がある場合には、外国人自身で納税することになるので注意が必要です。
そして万が一、期日までに税金を納めることができなかった場合は以下のようなペナルティが段階的に発生します。
① 延滞税の加算
延滞税とは、納税期日から経過した日数に応じて自動的に納税額に加算される税金です。
こちらは納税期日を1日でも過ぎると発生します。
② 督促状の送付
納税期限を過ぎると、支払いを督促する書状が届きます。
万が一延滞したことを忘れていた場合も、この督促状が届けば直ちに支払いにいきましょう。
③ 財産の差し押さえ
督促状が届いても納税手続きをしなかった場合、生活に最低限必要な衣服や食料品を除き、家具家電、アクセサリーなど、あらゆるものが税務署によって差し押さえられます。
④ 差押財産の換価
すぐに滞納額を納めれば、差し押さえられた財産は返してもらうことができますが、支払いが困難な場合は、差し押さえられた財産が売却され、納税に充てられます。
また、外国人の場合、滞納経歴があると、在留資格の変更や更新の際に不利になってしまいます。
受け入れ企業が気をつけるべきことは?
外国人労働者が支払う税金に関して、受け入れ企業が気をつけるべきことは3つあります。
まずは住民税・所得税を給与から天引きすること。
ただし、外国人の中には、給与から天引きされることの意味がよく分からない人もいるでしょう。
オリエンテーション等を行い、日本の税金のしくみをよく理解してもらう必要があります。
次に、日本で転職する場合。
日本人でも同様ですが、転職をする際は、所得税と住民税についての手続きを行わなければいけません。
また、退職・再就職の時期で手続きが変わります。
住民税は、退職日と再就職日の間に期間があるかどうかで手続きが変わります。
退職した翌日に再就職した場合は、退職した会社で「源泉徴収票」をもらい、転職先の会社に提出することになります。
その後、市町村から住民税の明細と納付書が送られてくるので、それを転職先の会社に提出、という流れになります。
こうすることで、新しい会社の給与から、引き続き住民税を天引きしてもらうことができます。
退職後に一定期間離職する場合は、その期間分の住民税は、外国人自身で納付する必要があります。
所得税は、退職日と同じ年のうちに再就職した場合、医療費の控除証明書、退職した会社の源泉徴収票の2つを新しい会社へ提出すれば、会社側が手続きをおこなってくれます。
つまり、受け入れ企業は転職元、先ともに、必要書類を用意、または受理する必要があるということです。
年内に再就職しなかった場合は、外国人自身で翌年の確定申告の時期に税務署で手続きをする必要があります。
いずれの税金に関しても、受け入れ企業が手続きのサポートをすることが重要です。
転職元の受け入れ企業は、外国人労働者に必要な書類を用意すること、また、手続きのサポートもぜひしてあげてください。
転職先の受け入れ企業は、外国人労働者が必要書類の準備をできているかどうか確認してあげることが大切です。
まとめ
日本に住み、働き、収入を得る以上は、外国人であっても、日本での納税が必須です。
しかし、日本の税金の制度には詳しくない外国人労働者も多いことでしょう。
まずは受け入れ企業が、外国人労働者の支払うべき税金やその納付方法、注意点についてよく理解し、説明やサポートをできる体制づくりをすることが大切です。
登録支援機関であるネクストドアでは、外国人労働者の税金やお金に関すること、生活面も、もちろんご支援、ご相談可能です。
疑問や不安のある方は、まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った支援計画やフォロー体制、外国人採用戦略をご提案いたします。
どうぞお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール