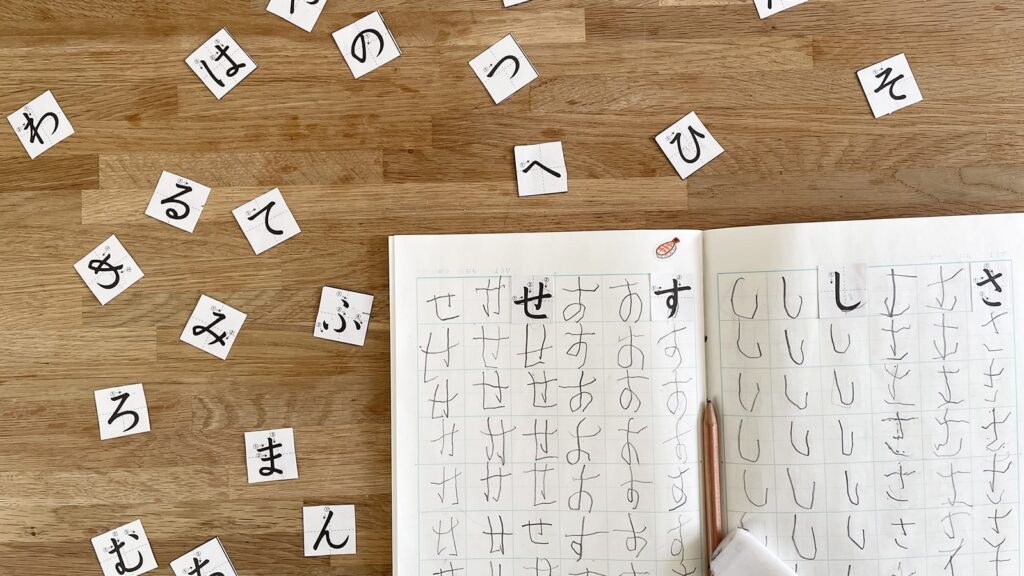
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
今、そして今後も圧倒的な人手不足が問題となっている介護の現場。
利用者は増え続けるのに対し、求人への応募者はそもそも少なく、せっかく採用した従業員の離職率も高いという悪循環で、需要と供給が全くつり合っていない状況です。
そんな人材不足を少しでも改善しようと整備された制度の一つが「特定技能」。
介護施設を運営されている方の中にも、この特定技能外国人の雇用を検討されている方は少なくないでしょう。
しかし、実際、外国人労働者は介護の現場で働けるのか?日本語能力は?
利用者の方々と上手くコミュニケーションが取れる?
など、色々ご不安に思われることもあるでしょう。
今回は特定技能外国人の日本語レベルに焦点を当て、介護現場で活躍してもらうために知っておきたいことをお伝えします。
特定技能の資格取得時点での日本語レベルはどのくらい?
そもそも特定技能の資格を取得するためには日本語の試験に合格しなければいけません。
(技能実習生からの移行の場合は条件付きで免除されます)
試験には、「日本語能力試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」の2種類があり、いずれかの試験を合格することが特定技能資格取得の条件となります。
日本語能力試験
日本語能力試験は、原則として、日本語を母語としない人を対象に日本語能力を測定し、認定することが目的。
こちらの試験においてN4レベル以上であると認定されれば、特定技能1号の資格が取得できます。
N4というのは、基本的な日本語を理解することができるレベル。
読むことに関しては、基本的な語彙や漢字を使って書かかれた日常生活の中でも、身近な話題の文章を、読んで理解することができる程度とされています。
また、聞くことに関しては、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できるレベルとされています。
(詳細は日本語能力試験公式ページへ)
国際交流基金日本語基礎テスト
国際交流基金日本語基礎テストとは、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定することを目的とした試験です。
こちらの試験においてA2レベル以上であると認定されれば、特定技能1号の資格が取得できます。
A2とは、
・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。
程度のレベルとされています。
(詳細は国際交流基金日本語基礎テスト公式ページへ)
介護の現場で必要な日本語レベルは?
どのような業種、仕事でもある程度の日本語能力は必要ですが、特定技能の分野の中でも、介護職は特に、日本語能力が求められます。
というのも、製造や清掃関連の仕事であれば、コミュニケーションの相手は基本的に職場の仲間や上司であることが多いでしょう。
飲食店などではお客様の応対をすることもありますが、聞くことや話す内容は大体決まっていることが多く、マニュアル化されていることも。
しかし介護に関しては、対人コミュニケーションが中心となったサービス。
職場の人同士はもちろん、利用者の方々との会話、時には利用者さんの家族やケアマネさんとも関わる必要があります。
また、会話だけでなく、日々の業務記録や報告書の作成など、読み書きの能力も必要。
そして何より、介護に関する知識や専門用語の理解も求められます。
特定技能の資格を持っているということは、前述の日本語試験いずれかに合格しているので、日常の場面で使われる最低限の日本語が理解できるレベルではあります。
ところが実際の現場では、より高度な日本語能力が必要で、日常生活に支障がない程度レベルでは、上手く対処しきれないことも多いのです。
実際の現場で起こっているお困りごと
介護は医療ではありませんが、利用者様の安心や安全を守る点では、医療施設と同じくらいの注意や気遣いが求められます。
また、現場のスタッフ間の連携も非常に重要。
会話のすれ違いや勘違い、理解不足があると、それが原因で、利用者様を危険に晒しかねません。
コミュニケーションが上手くとれないと、利用者さんからの不満にも繋がります。
また、外国人にとって特に難しいとされているのは漢字。
なにか伝達事項がある時に、普通に漢字を使った文章でお知らせやメモ書き、記録を書いて渡しても、なかなか漢字を完全に習得している外国人労働者はいません。
内容が理解できず対応が遅れてしまったり、求めていることと全く違う行動をしてしまったりすることも考えられます。
外国人労働者に何かをお願いする時や伝達する時は、必ず相手がよく理解しているかどうかの確認をするようにしましょう。
どのように教育すれば良い?
ただ、こうした問題は本人の勉強不足というより、現場特有のやり取りや用語、専門知識が求められることが主な原因です。
そうした現場ごと、業務内容ごとに必要な知識や用語、読み書き能力、会話力に関しては、現場で実践しながら身につけていくほかありません。
始めのうちは、一緒に働く仲間や上司がサポートにつき、このような時はこう対応する。
こんなことを聞かれたらこう応対する、といった実例を、体験しながら学んでいくのが一番です。
それに加え、テキストやeラーニングでさらなる日本語能力の向上を目指したり、介護に関する日本語の教材で学んだりすると、より即戦力として働けるようになるでしょう。
そうした教育、学びの機会を、受け入れ企業が作ってあげることも重要です。
より現場で役立つ日本語を効率よく学んでもらうためにも、できるだけ企業側が寄り添い、サポートしながら育成する気持ちを持つことが大切です。
まとめ
介護福祉士の国家資格を取得すれば、外国人労働者でも日本での永続的な就労が認められる介護職。
それ故に、資格取得のための勉強期間として、まずは特定技能介護で経験を積むという人もいるでしょう。
介護施設側としても、そのような人が増えてくれたらありがたいですよね。
ところが、外国人労働者の日本語レベルは本当に人それぞれで、特に介護の現場で求められる日本語は高度とされ、外国人にとってはかなり難易度が高いのです。
そのような外国人労働者にも即戦力として活躍してもらうには、この日本語能力の向上が不可欠。
受け入れ企業もサポートし、試験用の日本語ではなく、実際に現場で使える日本語の習得を支援することが大切です。
直接仕事に関わること、作業や業務内容だけでなく、日本語の教育・育成にも力を入れるべきでしょう。
とはいえ、ただでさえ人手不足で余裕がないのに、そこに時間を割けないという施設様もあるでしょう。
そんな時は、ぜひネクストドアにご相談下さい。
60分無料の「外国人採用戦略診断セッション」で、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った外国人採用戦略や支援計画をご提案いたします。
外国人採用に対する不安や疑問も解消できますよ。ぜひ、お気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール









