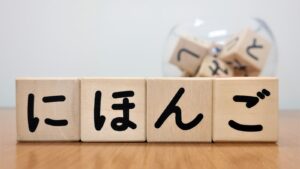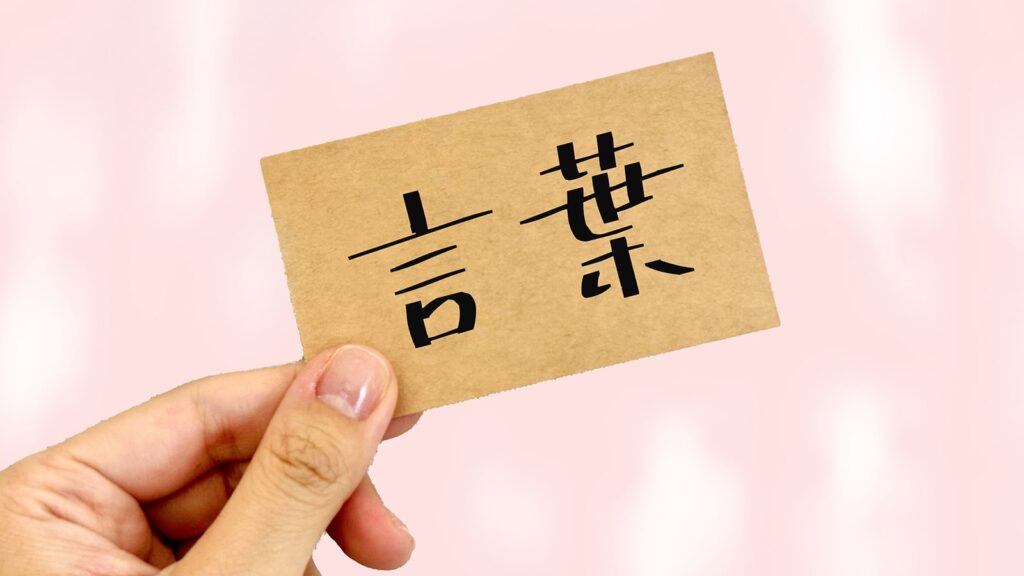
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
日本の労働現場では、特定技能を持つ外国人労働者が増加しています。
特定技能の資格取得には、日本語能力検定N4レベル以上の合格が必須。
ある程度の日常会話は問題なく可能な日本語力を持っていますが、日本語特有の表現や敬語、カタカナ語、略語などに戸惑うことが少なくありません。
こうした言葉の壁が原因で、業務の指示が伝わりにくかったり、誤解が生じたりすることもあります。
そのため、外国人にも分かりやすい「やさしい日本語」を使うことが、職場のコミュニケーションを円滑にし、労働環境を改善するための鍵となります。
本記事では、外国人労働者が理解しづらい日本語の事例や、その言い換えの方法などを具体的に紹介します。
これから外国人労働者を採用しようという企業様や、雇用中の外国人労働者とのコミュニケーションにお悩みの方は、ぜひお読みください。
日本語の敬語:丁寧さを保ちながら分かりやすく
敬語は、日本語を学ぶ外国人にとって非常に難しい部分です。
尊敬語、謙譲語、丁寧語という3つの敬語の使い分けは複雑で、状況に応じて適切な表現を選ばなければならないため、特定技能資格を持つ外国人でも戸惑うことが多いでしょう。
例えば、ビジネスシーンでよく使われる「~していただけますでしょうか?」という表現は、丁寧でありながら、外国人にとっては複雑なのです。
これを「~してください」とシンプルに言い換えることで、相手に丁寧さを伝えつつ、理解しやすい表現になります。
また、「お疲れ様です」や「よろしくお願いします」など、日常業務で使われる慣用句も、状況によって意味が変わるため、外国人にとっては難しいものです。
これらの表現も、「お仕事お疲れ様です」や「どうぞよろしく」などと、具体的な言葉を付け加えたり、言い換えたりすることで、意味が伝わりやすくなります。
ポイントは、できるだけ具体的かつシンプルな表現で、何を意味するかを明確に伝えること。
外国人が安心してコミュニケーションを取れるように工夫しましょう。
略語やカタカナ語:日常でよく使われる言葉の解説
日本人は日常的に略語やカタカナ語を多用しますが、外国人にはこれらが理解しづらいことが多くあります。
例えば、ビジネスの場では「リモートワーク」や「コスパ」といったカタカナ語が頻繁に使われますが、これらは外国人にとって分かりにくい表現です。
「リモートワーク」は「在宅勤務」や「遠隔勤務」、「コスパ」は「費用対効果」という言葉に言い換えると、より具体的に意味が伝わりやすくなります。
(もちろん、これらの言葉の意味を、その外国人の母国語で説明できれば良いのですが…)
また、「プレゼン」は「発表」、「アポ」は「面会予約」など、日常的に使われる略語を、できるだけ単純な日本語に置き換えて説明することが大切です。
カタカナ語や略語は日本人同士の会話で便利ですが、外国人が理解しやすい言葉に置き換えることで、職場のコミュニケーションがよりスムーズに進むでしょう。
尚、「プレゼン」はそのまま略さず「プレゼンテーション」と言えば伝わりますが、日本で日常的に使われているこのようなカタカナ略語の中には、略す前の言葉自体が「和製英語」の場合もあり、外国人には通じない場合があるので注意が必要です。
外国人が戸惑いやすい日本語英語とその解説
日本語には「和製英語」や「日本語英語」と呼ばれる、英語をもとにした造語が多く存在しますが、これらの言葉は外国人にとって非常に混乱を招きがちです。
例えば、「サラリーマン」という言葉は、日本では「会社員」を意味しますが、実は英語ではなく、外国人にとっては馴染みがない表現です。
これを「会社員」と言い換えることで、より分かりやすくなります。
ちなみに英語では「office worker」が近いかと思います。
同様に「コンセント」は、日本語では電源プラグのことを指しますが、英語では「Consent(同意)」という意味になります。
外国人にとっては、これが非常に紛らわしいため、「電源プラグ」などと明確に伝えることが大切です。
このように、和製英語は外国人に誤解を与える可能性があるため、できるだけ具体的な日本語表現に置き換える、もしくは正しい英語で伝えることを心がけましょう。
日本語特有のあいまいな表現とその言い換え
日本語には「あいまいな表現」が多く、これも外国人にとって理解しにくい要素の一つです。
例えば「ちょっと待ってください」や「まあまあです」という表現は、使う場面や話し手の意図によって意味が大きく異なることがあります。
これらのあいまいな言葉は、外国人には曖昧すぎて意図が伝わりにくいため、もっと具体的に表現することが重要です。
「ちょっと待ってください」は「数分お待ちください」や「5分ほどお待ちください」と時間を示すことで、相手に具体的な時間感覚を伝えることができます。
また、「まあまあです」という評価も、「普通です」や「良いです」「問題ありません」と、意図を明確にする言葉に変えることで、外国人にも理解しやすい表現になります。
あいまいな表現を避け、具体的に説明することで、外国人との意思疎通が円滑になります。
まとめ
この記事では、特定技能外国人が理解しやすい「やさしい日本語」に言い換える方法について解説しました。
敬語や略語、カタカナ語、和製英語、あいまいな表現などは日本語特有の言葉の文化。
外国人にとっては難解な部分です。
例えば、複雑な敬語は簡潔な表現に、カタカナ語や略語は単純な日本語に置き換え、あいまいな言葉は具体的な説明にするなど、少しの工夫で外国人との円滑なコミュニケーションが実現します。
やさしい日本語を使うことで、外国人労働者が働きやすい環境を提供し、企業にとっても生産性向上が期待できるでしょう。
特定技能外国人雇用のプロ、登録支援機関である当社は、採用戦略のご相談や採用支援だけでなく、採用後の様々な手続きや支援計画の作成、支援実施も行います。
日本語教育や、職場でのコミュニケーションに関するアドバイスやサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。
そしてまずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った外国人採用・育成戦略、支援計画やフォロー体制をご提案いたします。
疑問や不安のご相談だけでも、どうぞお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール