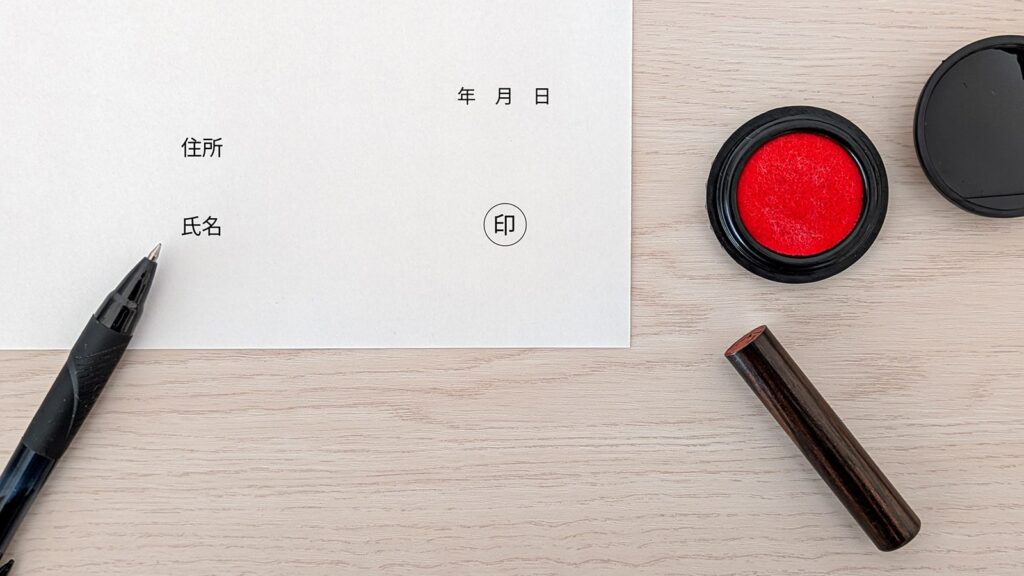
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
まもなく、2025年4月より、特定技能制度に関する基準省令の一部が改正され、新たな運用が始まります。
これにより、外国人材と地域社会がより円滑に共生できる仕組みが強化され、受け入れ企業にも新たな取り組みが求められるようになるのです。
特に、地方自治体の共生施策への協力や、外国人の生活支援体制の整備が重要なポイントとなります。
本記事では、改正のポイントを押さえながら、協力確認書の概要や提出方法、支援計画の作成、登録支援機関との連携について詳しく解説。
今後はじめて特定技能外国人を採用する企業様も、すでに雇用中の企業様も、ぜひともご確認いただきたい内容です。
外国人と地域の共生社会の実現のため、受け入れ企業に求められる取り組みとは?
2025年4月より改正される特定技能基準省令では、外国人と地域社会が円滑に共生できる環境づくりがより重視されています。
受け入れ企業には、特定技能外国人が安心して働き、暮らせるための支援が求められており、特に地方公共団体が推進する共生施策への協力が義務的な要素となります。
具体的には、日本語学習支援や生活オリエンテーションの実施、行政サービスの案内、地域のイベントや行事への参加促進など、多岐にわたる支援が必要です。
また、外国人本人だけでなく、地域住民との関係性構築にも配慮することが重要。
外国人材の安定した就労・定着には、職場だけでなく、生活環境全体をサポートする視点が不可欠なのです。
こうした包括的な支援により、地域に根ざした共生社会の実現が期待されています。
受け入れ企業にとっても、優秀な人材の長期雇用につながる大きなメリットとなるでしょう。
協力確認書とは?概要と提出方法について
協力確認書とは、特定技能外国人を受け入れる企業が、外国人の生活基盤の整備を目的とした地域の共生施策に協力する意志を示す書類です。
この確認書の提出が、2025年4月から原則として義務化され、出入国在留管理庁に提出する在留資格変更や更新申請時の必須書類となります。
協力確認書は、外国人の住居および勤務場所を所管する市区町村への申請が必要。
市区町村は、企業に対して協力を要請することができ、企業はその内容を踏まえて確認書の交付を受ける必要があるのです。
提出するタイミングは、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前。
もしくは、既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前となります。
提出方法としては、申請書類に添付する形でオンラインまたは窓口で提出するのが一般的。
この仕組みにより、受け入れ企業が地域社会と連携しながら外国人を支援する体制の整備が進みます。
協力確認書は、企業の信頼性や責任感を示す重要な書類であり、外国人との共生社会の実現に向けた第一歩といえるでしょう。
また、特定技能の雇用に関わる従来からの書類や届け出も、4月から新様式に変わるものがあるので要注意。
最新の書類データは必ず出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
(出入国在留管理庁:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html)
支援計画の作成と実施について
特定技能制度において、受け入れ企業は外国人材の安定した就労と生活を支えるための「支援計画」を策定・実施する義務があります。
また、2025年4月からの省令改正では、地方公共団体が実施する共生施策の内容を十分に踏まえた支援計画の作成が求められます。
支援計画には、就業前オリエンテーション、日本語学習支援、生活に関する案内(医療、交通、買い物など)、相談体制の整備、地域交流の促進といった具体的な項目が含まれています。
これらの支援は、外国人が新たな生活にスムーズに適応するための重要なステップであり、また、企業側にとっても人材の定着率向上や職場の安定化につながる要素と言えるでしょう。
支援内容は、実効性と継続性を持たせることが求められ、形式的ではなく実際の生活支援として機能する必要があります。
地域社会と連携した支援体制の構築は、共生社会の実現に欠かせない要素なのです。
登録支援機関との連携について
特定技能外国人の支援において、受け入れ企業は登録支援機関と連携することで、より専門的かつ実効性のある支援を行うことが可能になります。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人・団体で、外国人への生活支援や相談対応などの業務を専門的に担います。
企業がこれらの支援業務を登録支援機関に委託する場合でも、支援計画の策定とその適切な実施状況の確認は企業の責任です。
つまり、委託すれば終わりではなく、定期的な報告や情報共有を通じた密な連携が必要。
また、登録支援機関の選定にあたっては、実績や支援内容の充実度、対応言語なども考慮することが重要です。
信頼できる支援パートナーとの協働により、外国人材の生活基盤が安定し、企業としても安心して受け入れを継続できます。
地域との協力も含め、企業・支援機関・自治体が一体となった体制整備が、今後の制度運用のカギとなるでしょう。
まとめ
2025年4月の特定技能基準省令改正により、受け入れ企業は特定技能外国人と地域社会との共生をより積極的に支援することが求められます。
協力確認書の提出義務化や、地方公共団体の施策を踏まえた支援計画の作成、登録支援機関との連携強化が重要なポイントです。
これらの取り組みを通じて、外国人が安心して働き暮らせる環境づくりが進み、企業にとっても人材の定着や信頼性向上につながる好循環が期待されます。
登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。
採用戦略のご相談や採用支援だけでなく、採用後の様々な注意点やアドバイス、支援実施のサポートも行います。
まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った外国人採用・育成戦略、支援計画やフォロー体制をご提案いたします。
疑問や不安のご相談だけでも、どうぞお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール

-
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160
最新の投稿
 外国人の日常2025年4月1日4月に特定技能基準省令の一部が改正!その概要と、提出が義務化される「協力確認書」とは?
外国人の日常2025年4月1日4月に特定技能基準省令の一部が改正!その概要と、提出が義務化される「協力確認書」とは? 介護2025年3月31日【福岡のデイサービスで活躍中!】
介護2025年3月31日【福岡のデイサービスで活躍中!】 免許・資格2025年3月28日外国人労働者受け入れ政策の過去・現在・未来 ~制度の変遷と企業が抑えるべきポイント~
免許・資格2025年3月28日外国人労働者受け入れ政策の過去・現在・未来 ~制度の変遷と企業が抑えるべきポイント~ 免許・資格2025年3月27日特定技能外国人財の定着には1号から2号への移行がカギ!その違いと移行戦略について解説
免許・資格2025年3月27日特定技能外国人財の定着には1号から2号への移行がカギ!その違いと移行戦略について解説







