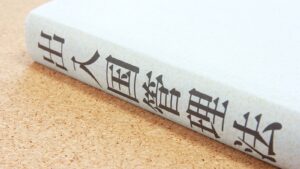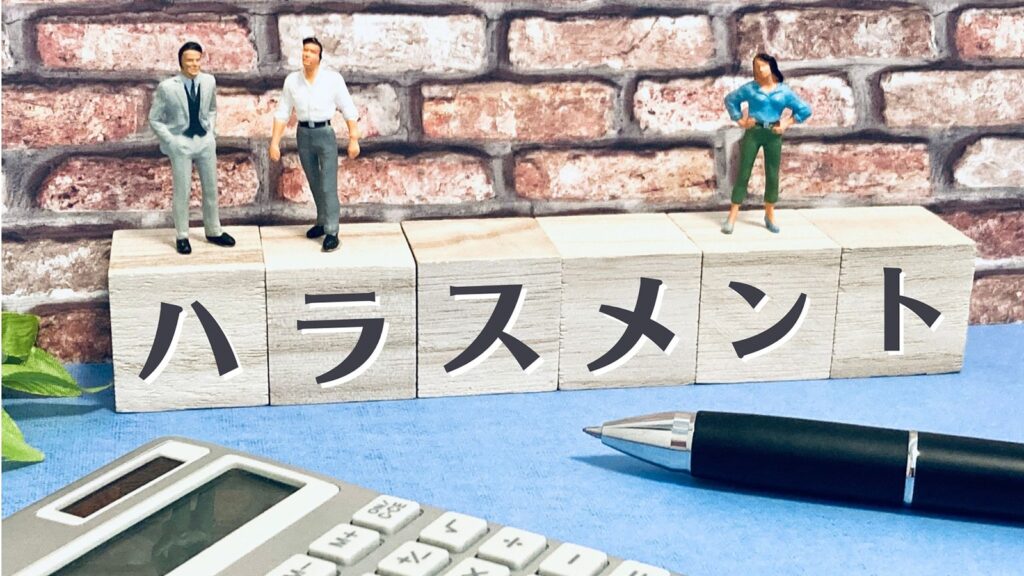
外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
昨今、何かと話題になる「ハラスメント」。
セクハラやパワハラ、カスハラ等、最近の日本では次々と新しいハラスメントが生まれていますが、これらは決して日本だけの問題ではありません。
外国人労働者の雇用に関しても、ハラスメントは無視できない問題です。
異なる文化や価値観を持つ外国人と働く中では、日本人とはまた違った点への注意も必要となります。
日本では問題とされにくい言動が、外国人労働者にとっては深刻なハラスメントとなることもあるのです。
企業がこうした違いを理解し、適切に対処することは、健全な職場づくりだけでなく、優秀な人材の確保・定着のためにも欠かせません。
本記事では、国際的な視点でハラスメントへの理解を深め、その対策について考えます。
これから外国人を採用したい企業様も、すでに雇用中の企業様も、改めてハラスメントについて考えるきっかけとしていただければ幸いです。
日本と海外では「ハラスメント」への意識と罰則に違いがある
日本では近年、職場でのハラスメントに対する意識が高まりつつありますが、欧米諸国では以前から厳格な法的措置が取られています。
例えば、フランスでは1992年にセクシュアルハラスメントに関する刑法が制定され、2012年には罰則が強化されました 。
一方、日本では2020年にパワーハラスメント防止法が施行され、企業に対策が義務付けられました。
このように、各国でハラスメントに対する法的枠組みや罰則には違いがあります。
外国人労働者は母国の厳しいハラスメント規制を背景に持つ場合が多く、日本の職場での些細な言動でも敏感に反応する可能性が。
そのため、企業は国際的な基準や各国の法制度を理解し、適切なハラスメント対策を講じることが求められます。
これにより、外国人労働者が安心して働ける環境を整備し、企業全体の生産性向上にもつながるでしょう。
国によって「ハラスメント」とされる言動の違いとは?
文化や社会的背景の違いにより、ハラスメントとみなされる言動は国によって異なります。
例えば、日本では(近年は嫌がる世代も多いようですが)上司が部下を飲みに誘うことは、一般的なコミュニケーションとされることが多いでしょう。
一方で、欧米では業務外の誘いがプライベートの侵害と受け取られ、ハラスメントと捉えられることがあります。
また、日本では、その人との関係性によってはある程度許される、冗談として捉えられるようば外見や年齢、性別に関するコメントも、海外では個人の尊厳を傷つける行為として重大な問題となる可能性が。
さらに、宗教や文化的背景に関する無理解からくる言動は、外国人労働者にとっては特に差別的に捉えられ、ハラスメントまたはヘイトにも感じられるリスクがあります。
企業は、これらの文化的差異を理解し、多様な価値観を尊重する職場環境を整えることが重要です。
具体的には、多文化共生のための研修を実施し、従業員全員が異文化理解を深める機会を提供することが良いでしょう。
まずは「無意識のハラスメント」を防止することが重要で、それが円滑なコミュニケーションにつながります。
受け入れ企業がとるべきハラスメント対策とは
とはいえ、ハラスメントを気にしすぎて会話がしづらくなるのも良くありません。
そこで、どういう言動がハラスメントとなってしまうのか?を具体的に知ることで、コミュニケーションがとりやすくなるでしょう。
そのためにも、受け入れ企業が、多文化共生の視点からハラスメント対策を強化する必要があります。
まず、全従業員を対象にしたハラスメント防止研修を定期的に実施し、異文化理解を深めることが重要。
次に、ハラスメントに関する明確な社内ポリシーを策定し、多言語での周知を行うことで、外国人労働者も含めた全員が理解しやすい環境を整えます。
また、匿名で相談できる窓口を設置し、被害者が安心して報告できる体制を構築することも効果的です。
さらに、ハラスメントの兆候を早期に察知し、迅速かつ適切に対応するための内部調査チームを設けることも有効でしょう。
これらの対策を通じて、外国人労働者が安心して働ける職場環境を提供し、企業全体の信頼性と生産性の向上につなげることができます。
ハラスメント対策が進んだ職場には多くのメリットが
ハラスメント対策を積極的に推進することは、企業にとって多大なメリットをもたらします。
まず、職場環境が改善されることで、外国人、日本人問わず従業員の満足度とエンゲージメントが向上し、離職率の低下につながるでしょう。
また、多様なバックグラウンドを持つ外国人労働者が安心して働ける環境は、企業のダイバーシティを高め、イノベーションの創出を促進。
グローバル企業としての評価を上げることにもつながります。
さらに、ハラスメントの防止は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要であり、企業イメージの向上や優秀な人材の確保にも寄与します。
加えて、ハラスメントによる法的リスクを未然に防ぐことで、訴訟費用や損害賠償といった経済的損失の回避にも。
このように、ハラスメント対策の徹底は、企業の持続的な成長と競争力の強化に不可欠であり、全従業員が安心して働ける職場づくりの基盤となるのです。
まとめ
外国人労働者を受け入れる企業にとって、ハラスメントへの理解と対策はとても重要です。
国や文化によって「ハラスメント」と感じる言動には違いがあり、何気ない一言やジェスチャーが、時に相手を傷つけてしまうこともあります。
たとえば、ミャンマーではドアの開閉に大きな音を立てたり、足音を響かせる行為が無礼とされる一方、日本では軽いボディタッチでも不快に感じる方が少なくありません。こうした文化の違いを知り、互いの価値観に歩み寄ることが、職場の良好な関係づくりにつながります。
私たちも、相互理解を深めるために勉強会や意見交換の機会を設けています。日々の積み重ねが、安心して働ける職場環境をつくり出す土台となると感じています。
こうした取り組みの先にあるのは、信頼関係の構築、チームの一体感、そして結果としての生産性の向上。人材が「定着」する職場には、こうした見えない努力が息づいているのかもしれません。
まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った外国人採用・育成戦略、支援計画やフォロー体制をご提案いたします。
疑問や不安のご相談だけでも、どうぞお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール

-
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160